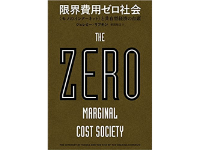医薬品市場の現状
医薬品市場は医師による処方箋が必要な医療用医薬品と、薬局で買える一般用(OTC)医薬品に分類される。前者の市場規模は10兆円であり、後者が8千億円と診療報酬の関わる医療用医薬品の市場規模が圧倒的に大きい。
薬価が極端に高い医療用医薬品が保険で賄われることで、医療費が圧迫されつつある。
新薬の薬価が高くなるのも理由は、医薬品や生産工程の高度化により臨床試験で承認されるための新薬の開発費や投資の回収のために資金が年々高くなっているからだ。この臨床試験では、薬の効きが個々の患者間の誤差に紛れない程度の患者数を集める必要があり、試験を実施するために相応の費用がかかる。
また、一般的な臨床試験にかかる医薬品のほかに、希少疾患用の医薬品がある。医薬品マーケティングの観点からは小さな市場で成功を収めて徐々に疾患の対象を広げていく適応追加という方策が定石である。希少疾患ではそもそも患者数が集められないので、通常の臨床試験が行えない。ただし、薬としてのニーズがあり、開発を進めないといけないという背景からがあるので極少数で臨床試験が行われる。
医薬品市場の展望
逆の発想としては、近年、がん分野で症状ではなく特定の遺伝子の変異に着目した遺伝子検査が保険収載されたことが記憶に新しい。医薬品と臨床試験に参加する被験者の対応を多対多にすることで、臨床試験の効率化が行われている。開発や臨床試験の規模が大きくなると、新薬の承認を得られるのは巨大企業のみとなるだろう。
このような背景のもと、新薬の承認薬価が上振れする状況の一方で、皆保険制度的に破綻を来さないように既存薬の薬価を下げることが行われている。保険償還の仕組みにより、高額な医療費であっても患者負担は安価に提供されている。本来、保険制度は国民の医療へのアクセスが目的である。しかし、新薬とそれ以外の既存薬と概念的に分けられ何らかの政策意図が働くとすると、保険制度が再定義されていくのではないかと私は考えている。
つまり、既存薬の薬価を下げていく一方で、希少疾患やがん、人の命に直結する医療に保険の財源を回していくと、新薬の開発のための臨床試験に関わる医療に保険の財源が使われる。臨床試験と皆保険制度が結びついた世界が1つ。 そしてももう1つが、薬価の下げ切った既存薬である。現状、病院で医療用医薬品が処方する方が、OTC薬を購入するよりも安い。逆ザヤになっている。この逆ざやを解消すれば、医療用医薬品として保険償還される費用をOTC市場に移行させることができる。そうすることで保険医療費の財源をある程度確保できるようになるのではないか。健康保険薬局やスイッチOTCの傾向などもみていると、近いうちのいつかどこかでこの逆ザヤにメスを入れる瞬間が出てくると予想される。
これからの医薬品市場(私見・まとめ)
医療業界はグローバルで巨大な研究開発型の製薬企業とそれ以外の中堅メーカーに分かれるだろう。中堅以下の製薬メーカーのイメージは、上流からの製薬会社がエンドユーザーにかなり近い距離感で地域包括ケアへ取り組んだり、他業種と協業するパターンと下流からの調剤薬局チェーンがジェネリック薬の製造メーカーとなるパターンなどがある。ドラッグストアがプライベートブランドをOEMで作ることもあるだろう。地域ごとの特色があるので全国統一でというのはもしかしたら難しいかもしれないが、今とは全く違った製薬会社の業態も出てくるかもしれない。
(2019年6月)
(関連リンク)
市販薬あるのに病院処方5000億円 医療費膨張の一因