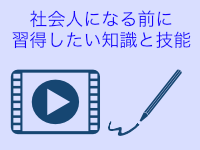コロナ禍でも時は流れます。会社では新入職員が入り、高校を卒業して大学生になる人もいます。今回のテーマは、なるべく社会で役立つ知識やスキルを身につける方法です。大学の今やZoomを使用してワードでレポートを提出くらいまでは行っています。アルバイトもしていれば、一般的な接遇などもマニュアル化されていることでしょう。それでも、社会人1年生を見ていると困っている姿を見ます。就職活動を3年、4年で行うとすると、実質自由になる時間は1年、2年の2年間くらいしかありません。もちろん、就職だけが全てではないですが、YouTubeでもスモールビジネスでも、自分で何かをしたいと思った時に、後から後悔しないように、今必要とされるスキルを身につける方法をご紹介します。
目的を固める方法か伝える方法か?
現実としては、スキルの習得という場合、ツールの使い方を考えることが多いが、実は、ツールを使う前段に問題を抱えていることも多い。何をしたいのか、何をやりたいのかが漠然としていて、それをまとめることができないということもあります。社会人の場合は、雇用関係がある以上、どこかで適性を見て入社していることなので、ある程度言いたいこと、表現したいものがあるだろうということで、ツール関係の使い方に絞ります。
ツールの使い方
ツールの使い方は、いろいろな資格やスクールなどの情報が溢れかえっています。結局、「どの情報を信じればいいのか」、「どこが元になっているか」が分からなくなります。恐ろしいことに、結局、分からない人は分からないままで過ごしてしまうのかもしれません。何かしら興味を持った人は、自分から調べることになるのかもしれません。知識や理解のある人がマンツーマンで向き合って教えるのが一番手っ取り早いのかもしれません。お互い時間やお金を無駄にしないためにも、誰かに聞くよりも先に、そのツールや分野が情報を知りたい人に合っているか、確かめた方がいいように思います。前提となる基礎の基礎は、1日から数日かければ下記のような場所で情報が得られます。
Apple Store
Apple storeは言わずと知れたAppleの実店舗になります。一見、製品を売るだけの場所のように思うかもしれませんが、実は、製品の使い方を含めたサポートをしています。Apple製品に限ると言うことになりますが、学びの場として、プロダクト、写真、ビデオ、音楽、プログラミング、アート&デザインの6つが準備されています。
Windows製品と異なりApple製品は作りたいものを最後まで作るためのアプリケーションを一通り揃えています。専門的になってくると購入した状態では物足りないこともあるかもしれません。もっとも、たとえWindowsしか持っていなかったとしても、製品の使い方を説明されることで、写真やビデオ、音楽の制作工程が分かるようになります。例えば、ビデオのセッションではMacに予め入っているiMovieの説明がありますが、制作会社ではAdobe製品を使うことがほとんどだと思います。それでも、動画を一度も作ったことがないような方にとっては、製品を理解すると言うより、作り方を見るという気持ちで概略を理解するようにしたらいいと思います。特に仕事とは関係なくなるかもしれませんが、YouTubeなどで動画編集をしたい場合など初めの一歩としては理解しやすいと思います。
ちなみに、プロダクトはMacやiPhoneそのものの使い方になります。意外な設定方法もあるので、iPhoneを持っている方は一度尋ねてみてもいいかもしれません。
- Apple Store - 銀座
- Apple Store - 丸の内
- Apple Store - 渋谷
- Apple Store - 新宿
- Apple Store - 表参道
- Apple Store - 川崎
- Apple Store - 心斎橋
- Apple Store - 京都
Adobe
Adobeは知らなくても、「PDFファイル」を作った会社と言うと通じます。PDFに関して言えば、MacやWindowsなど特定の環境に左右されず、ほぼ同様の状態で文章や画像等を見ることができる電子文書フォーマットと言えます。元は1企業のファイル形式だったものが、2008年7月2日にISOと言われる国際標準化機構で国際規格として採用されました。そのため、官公庁や企業間のやりとりで広く使われています。パソコンを使っているならば、一度は使ったことがあるはずです。
アドビの社歴を見ていくと、パソコン、スマートフォン上のコンテンツ作成に大きな影響があることが分かります。黎明期には、パソコンとプリンタ間のデータをやりとりするアプリケーションの会社であったのが、イラスト作成のアプリケーションIllustrator、写真編集用のアプリケーションPhotoshopを発売し、印刷関係の業界標準となった。動画に関しても、Premiereと言う編集アプリケーションを販売している。パソコン機能の向上と共に、パソコン上でできる文字、画像、動画、音声など編集作業の業界標準となるようなアプリケーションを世に送り出しています。その間に、競合他社、いろいろな会社を飲み込む形で成長している。映像編集は、Premiere以外にもAppleではFinal Cut Proがありますが、開発者が同じ人であったります。
Adobeの躍進が、国際規格となるなどある程度オープンなものである一方、これらのアプリケーションを使用し続けないといけない状況があります。印刷に関しては活版印刷の頃から、動画に関してはフィルムの頃から、仕事として成立させるためのノウハウ、編集手法が蓄積されてきました。最近の動向としては、ByteDance(と言うよりTikTokの会社と言う方が分かりやすいかもしれないですが、)のような会社の躍進もあります。TikTokのような動画に特化したソーシャルネットワーキングサービスを持つ会社が自社のサービスに合わせやすいようにcapcutと言う動画編集アプリケーションも提供しています。新しい表現媒体が出てきたことで、もしかしたらイラストや動画などの編集手法も根本的に変わっていくのかもしれません。
印刷する画像や文字、映像に関しては、商業コンテンツに関しては、Adobeの製品が用いられることが多いのではないと思います。Adobe製品を使用した方が、まだまだ完成度が高いからです。それは、コンピュータが登場する以前から蓄積されたノウハウがパソコン上に再現されているからに他なりません。Adobeのサイトからチュートリアルと入門ページをリストにしました。製品そのものを使用するためというより、どのような工程が行われるのか一度見てみるといいかもしれません。
アプリケーションとしては下記が対応しています。
- Premiere Pro 入門 : いわゆる動画を編集するためのアプリケーションがPremiereです。
- Illustrator 入門 : イラストを作成するためのアプリケーションがIllustratorです。
- Photoshop 入門 : 写真などの画像を編集するアプリケーションです。
- After Effects 入門 : 映像編集用のアプリケーションなのですが、こちらはモーショングラフィックス(写真やイラスト動画に動きをつけたもの)などに使われます。VFXの業界標準ツールです。
- Adobe InDesign 入門 : いわゆるページもの(DTP;desk top publishing)を作成するためのデザインツールです。チラシや見開き程度であれば、Illustratorでもできますが、ページレイアウトや文字組版をするような印刷物の作成にはこちらが使われます。
昔は買い切りも出来ましたが、今は月額利用になっています。ただし、学生・教職員向けには、利用条件にあるように割引制度があります。
マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)
マイクロソフト オフィス系のアプリケーション(ワードやエクセル、パワーポイント)をどこまで使いこなせたら、一通りできることになるのかを考えてみたいと思います。大学でもレポートや宿題の提出でワードやエクセルを使うことはあるようです。ワードは少なくとも触れたことがない人はいないのではないか。エクセルになると実験をする理系の学科では数値の計算をしなくてはいけないので、それなりに使用する頻度があると思われます。学内もしくは学外、例えば学会で発表する機会があれば、パワーポイントも使う機会があると思います。特に、コロナ禍でオンラインが普及した状況を考えると、資料を作成する機会や発表することも多くなっているのではないかと思います。
パワーポイントに関しては、資料の作り方、ツールの使い方というより、中身が問題のこともあります。華美な装飾が内容を分かりにくかったり、アニメーションが多かったりし、結局何が言いたいのか分からない発表を見かけることがあります。それでも、敢えて、オフィス系のアプリケーションについても言及します。それは、マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)を持つ方から、スライド作成に関して知っていると便利なちょっとした小技を聞くことが多いからです。
MOSは、Microsoft Office製品の操作スキルを証明できる国際資格ということです。試験科目は、Word、Excel、PowerPoint、Access、Outlookの各アプリケーションについて、Officeバージョンごとにあります。試験は、本物のアプリケーションソフトをマウスやキーボードで操作して解答するそうです。参考までに、パワーポイントの試験範囲を見てみると、華美なほど機能を網羅しているように思います。
パワーポイントについては、伝えた内容をしっかりと定形のフォーマットに入れるようにしています。そうすると、レイアウトが自由な白板くらいのイメージになり、ほとんどパワーポイントとしての機能は使わないのですが、それでも、図形や印刷機能など知っていると便利なことはあります。
まとめ
どこから学べばいいのか、当たり前にあるものの背後に目を向けると、見えてくるものがあります。形のあるものは何らかの道具で作られています。特殊な伝統工芸などを除いて、一般に目に見えるくらい量産されているものであれば、コンピュータの補助を得ていると考えられます。パソコンやスマートフォン上で見られる、イラストや音楽、動画であれば、直接の作成者と道具の作り手に分業されているはずです。何か自分に足りないものを勉強したいと思ったら、どこかしらに取っ掛かりがあるはずです。そういう気づきを大事にしてもらえればと思います。
統計に関して、基礎を知りたい場合は、下記のリンクからご参照ください。電子書籍も作成しました。
(関連コンテンツ)
医療統計学が難しい理由
現場で役立つ医療統計スキル習得のための最短経路
臨床論文に出てくる試験デザインの分類と種類
文献によく出てくるt検定の種類、3つ。
検定の多重性について
標準偏差が分かるための正規分布。確率分布を理解して疑問を解決。
サブグループ解析でのハザード比(HR)の読み方
カプランマイヤーなどの生存時間解析で試験の背景比較がよくない訳
どれをインストールしたらいい?医療で使える統計解析ソフトウェア6選
電子書籍「医療統計入門 〜統計の基礎からt検定、 分散分析(ANOVA)まで〜」(iBooks/Kindle)